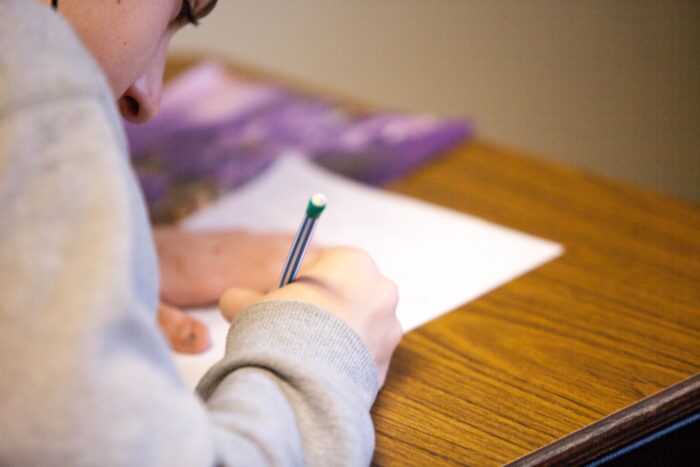- ホーム /
- 反社会的勢力関連
1 調査会社の視点
- 私たち調査員は、採用前のバックグラウンドチェックを日々こなしており、毎日何十通もの履歴書に目を通しています。
- そんな中で、履歴書から問題社員となり得る人すなわちヤバい人の共通点も浮かび上がってくるものです。その一例を紹介します。
2 こんな履歴書には要注意
- 履歴書の日付が抜けている。または全く違う日付
人事部の採用担当者であれば、履歴書の一番右上の日付が抜けている履歴書を見たことはあると思う。履歴書の日付はその履歴書を「応募先の企業に提出する日」を記入します。 つまり、郵送であれば「郵便局に持ち込む日」「ポストに投函する日」、持参するのであれば、企業を訪問する日を記入するのが正解です。
どの日付を書くのが正解かわかっていない人がいる事も少なくないが、やはり空白で提出してくるという意識からして、採用面接に臨む姿勢は低いと言わざるを得ない。
- 年齢や卒業年を間違っている
自分の年齢くらいは把握していなければおかしいと思うべきです。それを間違って記入していたり、学校の卒業年も違っているのは、いい加減で適当な性格の人が多いです。
- 住所が途中で終わっている。
こういう履歴書も見たことはあると思います。履歴書を書いている最中に何か別のことに気を取られたのか、続きの住所がわからない、など色々と推測は出来ますが、どういった理由であれ、最後に見直しをすれば書き漏れには気付けますし、続きの住所がわからないなんてものは言語道断です。注意力散漫なうえに常識が欠けていると判断されてもおかしくありません。
また、マンションやアパートに住んでいるのに、住所は番地までの記入でマンション名や部屋番号を書かない人も多いです。
昨今は個人情報保護と云われる時代ですが、採用面接を受けようとしている会社に対しても個人情報を出せないという意識を持っている人は不満分子になる傾向があります。
- 職歴がやたらと多く、短期間で退職している。
これは調査員じゃなくとも、「少しヤバそうだな」と感じる採用担当者は多いと思います。職歴が多い人や短期間で辞めてしまう人すべてを否定することはしません。ただ、傾向として「飽きっぽい」、「忍耐力が無い」という人が多く、なかには能力不足で退職勧奨されてきた人が多いのも特徴です。
- 記入項目をきちんと埋めない
履歴書には氏名住所、職歴のほかに免許・資格や配偶者の有無、扶養家族を記入する欄が設けられています。前述した通り個人情報保護を盾に書かないという人もいるかもしれませんが、採用面接を受けようとする誠実さは感じられません。
3 結論
- 上記のとおり、こんな履歴書を提出してくる人には注意を払っていただきたいのですが、あくまで調査員としての経験を加味した傾向です。
- なかには優秀な人材がいるのも事実であり、履歴書だけで採用するか否かを決めることは出来ません。面接での印象も重要ですが、バックグラウンドチェック(採用調査)で、前職での人柄、能力や退職理由を調べることをお薦めします。
https://www.ks110.com/
1 調査の必要性
- 暴力団排除条例等が成立し、企業として、反社会的勢力との関わりを未然に防ぐための調査をする義務があります。
- 取引開始時の取引先の調査、社員の採用時の調査、お客様の与信の調査について調査が必要になります。
2 インターネット
- 簡単な調査としては、インターネットにて「山田太郎 詐欺」等で検索をする方法があります。
- なお、最近では、元犯罪者の社会復帰の弊害になるとして、削除請求が認められることもなりました。
元犯罪者側の立場で、日本の有名なサーバーに「犯罪をしたのは事実であるが、既に〇年経過して罪を償っている。記事を残す社会的意義よりも、本人の社会復帰を拒むデメリットの方が大きい。」と削除請求をすれば多くの記事は削除されます。
犯罪歴の取り扱いは難しい問題です。大手企業としては、トラブルをさけるために、削除請求があれば比較的容易に削除を認めています。
3 新聞記事
- 有料の新聞記事サービスを利用して、過去の記事から、犯罪歴を調査する方法もあります。
4 経歴・職歴
- 刑務所に行っていれば、経歴・職歴が空きます。履歴書をもらうのも有効です。
- 空白があれば、本人に聞いてみて「裏付けがとれそうな答え」が返ってくるかがポイントです。
- 裏付けの取れない答えが返ってきた場合には、リスクとして査定すべきです。
5 知識(実名報道)
- 警察にも、報道機関にも、実名報道の基準があります。すべての犯罪が新聞記事で確認できるわけではありません。
- 新聞記事等で犯罪歴を確認できないとしても、その人が犯罪を犯していない証拠とはいえません。
6 知識(起訴猶予、執行猶予)
- 犯罪を犯した人が全て刑務所に行くわけではありません。
- 「犯罪を犯したけれども、刑事裁判にするほどではない。」と検察官が判断し、その裁量で起訴しない制度(起訴猶予)もあります。
- 刑事裁判になって有罪判決が出たが、執行を猶予されて刑務所に行かないですすむ執行猶予という制度もあります。
例えば、「懲役2年、執行猶予3年」という判決は、3年間悪いことをしなければ、刑務所に行かなくてよい。
逆に、3年以内に、懲役1年の有罪判決を受けた場合には、猶予された懲役2年と今回の懲役1年を足した合計3年の懲役を受けることになります。
- 初犯の多くは執行猶予となります。
- 刑務所に行っていないからといって、その人が犯罪を犯していない証拠とはいえません。
7 調査会社
- 疑わしい事件では、調査会社を使うか対象者の昔を知る人物(知人、勤め先、同僚)に直接取材するのが一番です。
- 犯罪を犯したかどうかまでは分からないかもしれませんが、その人柄は間違いなく分かります。
1 面接での印象は良くなかったが
- いつもご依頼いただいている企業さんからの案件でした。
- 最終面接まで残ったものの、イマイチ履歴書に書かれているような
「職場の人たちとのコミュニケーションが良好で、よく飲みにも行っている」
といった記載情報に少し首を傾げるような面接のパフォーマンスだったようで、
心配になり依頼という流れでした。
2 調査の結果
- 愛想もあり、コミュニケーションスキルはしっかりしているとのことでした。
- 心配していた面接でのパフォーマンスが低かった件は、
「最初は少し人見知りなところがあるから、しばらくすれば慣れてくるよ」と
前職での良い評が取れました。
- ご依頼主様はこちらの評価に安心され、採用することになりました。
3 採用その後
- 前評判通り最初の1ヶ月ほどは人見知りが出ているようで、まだまだ馴染めていませんでしたが、
日を追うごとに上手くコミュニケーションを取れるようになったそうです。
- 今では無事リーダー的ポジションにつき、会社に上手く貢献しているようです。
4 採用調査のもう一つの側面
- 前回の例のように悪い人を炙り出すだけではなく、「良い人財を取り逃がさない」といった性質もあります。
- いずれにせよ判断材料が増えることによって企業様の今後の寄与出来ます。
1 10年間勤務していたはずが
- 面接での受け答えはまずまず、だが時々専門用語を聞いたときの反応が気になる。
10年も経験がある割にはイマイチということでご依頼
2 調査の結果
- 新卒入社で10年在籍していたという会社は丸々嘘。
- 新卒ではあるもののわずか10日間しか勤めず、挙げ句無断欠勤のまま蒸発した とのことでした。
- 更には必然的に出来る空白期間で前科があることが判明
- 懲役5年ということでした。
3 調査その後
- 依頼主様は上記の結果に驚きを隠せませんでした。
- すぐさま不合格通知を出し、事なきを得ました。
4 まとめ
- 仮にこの人を採用してしまっていたら、きっと何か問題を起こしていた事でしょう。
- 再犯の可能性が高いです。
1 反社会的勢力について
- 反社に関するうわさを聞くことは少なくありません。
・「暴力団の知り合いが多い。」と言いふらす従業員
・取引先のA社の経営者は、暴力団である。
・強面の人間がよく出入りしている
など様々です。
2 暴力団排除条例
- 暴力団排除条例では、暴力団との取引を禁じております。したがって、企業としては、このような情報が出てきた場合には適切な調査と対応が必要です。
- 従業員の態度が悪く、解雇理由がある場合や、取引先の仕事に問題がある場合には、それを理由として取引の打ち切りを検討します。
- なお、暴力団排除条例は、不当な差別を禁じております。例えば、暴力団の事務所であると分かった場合に、電気ガスの供給の停止は許されますが、暴力団であるからといって、住宅の電気ガス等の契約を拒否することはできません。
暴力団だとしても、その人が個人として生活する手段までは奪えません。
3 社員への対応
- 取引先が暴力団である、もしくは従業員の一人が暴力団であるとのうわさが広がれば、社員に動揺が広がります。
- 会社として、社員にどういう方針で対応するのか、そして、誰がどのように対応するのかを早々に説明する必要があります。
4 先方への対応
- 経験上ですが、相手がどんな人であっても、理不尽な要求を飲んではいけません。
脅せば金を出すと思われると、要求がエスカレートし解決が難しくなります。
クレーマー等は、いろいろな方とトラブル を起こしています。彼らにとって、一番腹が立つ人物にならなければ、攻撃対象は別のところへ移ります。言うべきことは言っても大丈夫です。
- したがって、暴力団の疑いが出てきたとしても、会社としての対応を変える必要はありません。例えば、取引先の仕事に問題があれば、当然、仕事の発注を止めてもよいわけです。
- 極論ですが、「御社の取締役が暴力団であることが分かったので仕事を打ち切ります。」と回答しても大きなトラブルになりません。
暴力団にとっても、このような仕事の打ち切られ方は未経験ではありません。一番腹が立つ人物(会社)にならなないためにも、冷静な対応をするべきです。
もちろん、「本部(上司)の指示で、別の会社に仕事を依頼することになりました。」と単に結論を伝えるのがベストではあります。
- 逆に言えば、弱腰の姿勢を示すことはトラブルを大きくする可能性があります。
5 警察への相談
- 警察に、相手方が反社会的勢力であるかを回答してもらう制度があります。なお、警察にもしっかりとしたデータベースがあるわけではありません。警察に照会があれば、所轄の警察署に連絡したり、現地を見に行ったりして情報収集をした上で回答してくれます。
- 単に疑いがある程度では、警察も回答してくれません。したがって、相手方が反社会的勢力であると疑う根拠を示したうえで警察に問い合わせる必要があります。
この根拠を自力で集めるのは大変ですので、調査会社に依頼して、その根拠に代えることもできます。
6 結論
- 取引先が暴力団である、もしくは従業員の一人が暴力団であると疑いがある場合も、通常と同じように対応することになります。
従業員を退職させるのであれば、通常と同じく、事実確認、その後の本人からのヒアリング、そして、処分へと手順を踏みます。
- なお、問題が大きくならないように、取引先や、社員との面談の場面に、弁護士の立ち合いをお願いしてもよいかもしれません。
- 毅然とした態度、そして然るべき対応に尽きます。