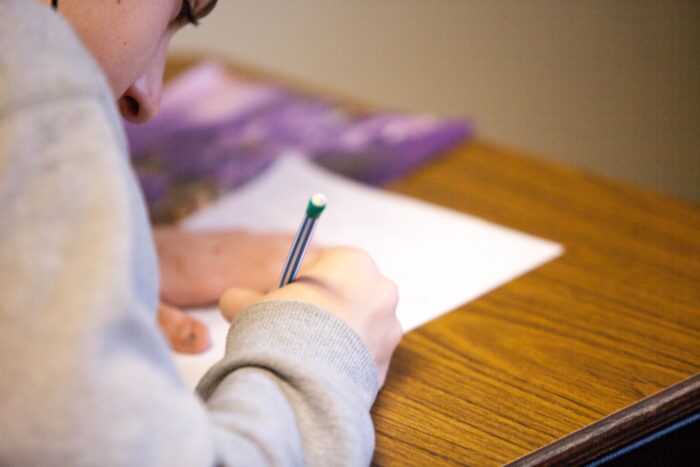1 電子契約と意思表示
- 電子契約では、契約の成立について、「●●@kk.com(の利用者)と、〇〇@kk.JP(の利用者)との間で契約が成立した。」その契約はこれですという形で、契約書がPDFで表示されます。
- 旧来の紙の契約書については、契約者の名前が書かれて、判子が押されます。契約当事者が、契約書に署名した事実は、その契約書どおりの契約を成立させようとする意思の存在を推察させます。
- これに対して、電子契約では、●●@kk.com(の利用者)が、承諾ボタンを押したことしか推察されません。
ここで、ポイントとなるのは、●●@kk.com(の利用者)が「契約を成立させる意図で、承諾ボタンを押したこと」か推察されるシステムになっているか。裁判で容易に立証可能になっているかが問題になり得ます。
2 契約の問題
Ⅰ.契約の成立
- 契約は、契約当事者の意思の合致で成立するとされています。つまりAさんが契約書通りの契約をする意思を持ち、Bさんも契約書通りの契約する意思を持っていたということです。
- 「契約する意思」を最も簡単に証明する技術が契約書です。旧来の紙の契約書については、契約者の名前が書かれて、判子が押されます。契約当事者が、契約書に署名した事実は、その契約書どおりの契約を成立させようとする意思の存在を推察させます。
- 例えば、売店で100円を渡してジュースを買うとします。契約書は取り交わしませんが、お客さんは「ジュース下さい。」と言って100円を渡します。これによって、お客さんは「ジュースを100円で買う。」との意思を示しています。
これに対して、店員さんは、100円を受け取ってジュースを渡します。これによって、店員は「ジュースを100円で売る。」との意思を示しています。
Ⅱ.電子契約における意思表示
- 電子契約では、●●@kk.com(の利用者)が、承諾ボタンを押したことは推察されます。
- しかし、●●@kk.com(の利用者)が「契約を成立させる意図で、承諾ボタンを押したこと」か推察されるシステムになっているか。裁判で容易に立証可能になっているか、これは大事な問題です。
- なお、実際のケースでは、契約書にしたがって、お金の支払いや、商品の移動がありますので、総合的には、「当事者は、契約書どおりの契約を成立させる意思を持っていた。」と認定されることも多いとは思いますが、電子契約を使うためには大事な問題です。
3 電子契約のポイント
Ⅰ.「契約を成立させる意図で、承諾ボタンを押したこと」か推察されるシステム
- 電子契約では、「●●@kk.com(の利用者)が、承諾ボタンを押した。」ことまでは、容易に認定できます。
- 次に、●●@kk.com(の利用者)が、「契約を成立させる意図」以外で、承諾ボタンを押すことがない仕組みが必要です。
例えば、「契約の承認ボタンを2度押させる。」「承認ボタンと拒否ボタンを用意して、承認ボタンを押したことを明確にさせる。」「契約書締結後に5分以内であれば、取消ボタンを用意する。」「契約後に、契約書をメールで送ったり、当事者の住所に送って、間違いがあればそのことを申告できるようにする。」等のシステムがあります。
Ⅱ. Ⅰを容易に立証できる機能
- システムはバーションアップしてきますので、当時の承諾のプロセスを記録化し、これを再現できるシステムが必要です。動画でもよいですし、写真入りで操作手順を示すマニュアルでもよいでしょう(「契約書を承認したと表示されるには、こういう操作をしなければ、このように表示されないこと」を説明したものが必要です。)
- 仮に、「契約書を承認したと表示されているが、これは、押し間違いの可能性はなのか。」が争点になる可能性が考えれば、これらが簡単に閲覧できる機能は必要です。
3 最後に
- 電子契約は非常に便利ですし、今後流行っていくと思います。
- しかし、どういうリスクがあるのかはきちんと理解した上で使うことをお薦めします。